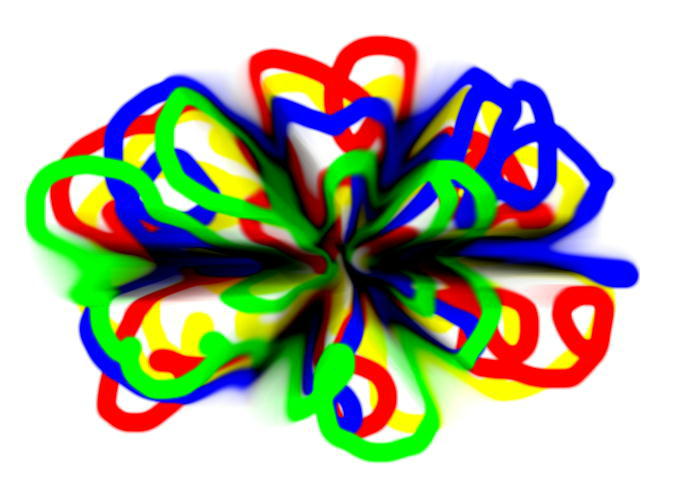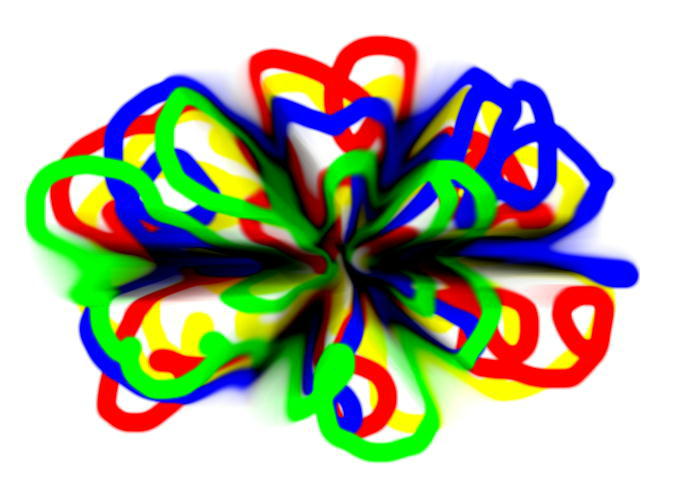考えてくれた人
横田は、大切にしている。
「君のこと、考えてるから」
と、男は見つめた。
「結婚はしたくないけど、子供は欲しいな」
と、女は逸らした。
男は拒絶されたと感じ、離れていった。
いくじなし、と女は追いかけなかった。
数年して、男が家庭をもったと聞いた。
うそつき、と女はひとり泣いた。
ある年、突然、男から連絡があった。
「今、近くの公園まで来てる。遊びにいってもいいか」
女は、老親と暮らしていたし、昼間に間違いもないでしょう、と受け入れた。
男は、親子連れだった。
世間話から、共通の友人たちの消息へと進むうち、いつか話は弾んだ。
奥さんのことを尋ねると、男の顔が曇った。
「まじめ一方で物足りない。そう言われたよ」
「夫婦喧嘩? ふふ、あちら立てればこちらがってやつじゃない。あなたにはあなたの良さがあって、それでいいのにね」
「ありがとう。なみだ出そうだ」
実は、と男は切り出す。
彼の妻は、新しい男をつくって逃げてしまったのだそうだ。
女は、虚を突かれ、少々混乱したが、穏やかな笑顔をすぐ取り戻した。
「今日は突然だったのに、ありがとう。ああそうだ、これから近所に用事があるんだけど、少しのあいだ、ぼうずを預かっておいて欲しいんだ。迷惑かな」
「いいわよ。おりこうそうねえ。 ・・きみ、おとなにしてるけど、この傷は何かな? すごい腕白なんでしょ? おばさんはお父さんの昔からのお友達だから、なんも遠慮いらないよ。お庭で遊んでらっしゃい。お菓子だってまだあるう」
「君のこと、忘れないで、助かった」
男は、帰ってこなかった。
幼児のしょっていた袋を調べると、姓名、生年月日、失職のことや無理を言う手紙、そしてくたびれきったような数枚の紙幣が挟んであった。
これが、母子家庭だった横田の「父」の事情だ。
横田は、信じている。
としても、本人の当時の記憶は曖昧だろう。かなしい事情であるほど、蒸し返されることも少なかったはずだ。微妙にずれながら、物語になっていったのかもしれない。
横田は「母」を、これ以上ないくらい大切にしている。
|