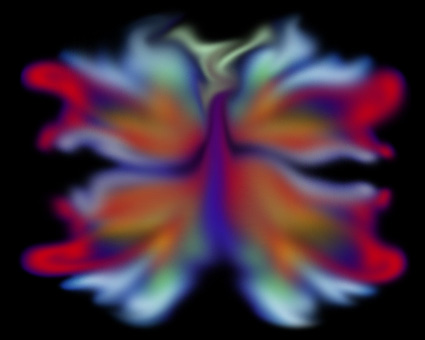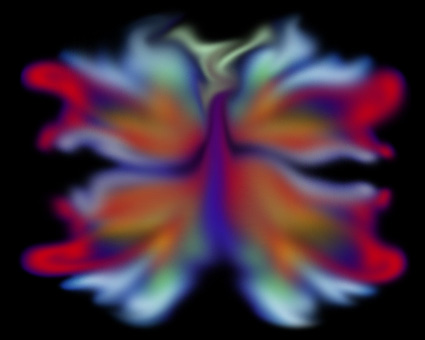検証
「行ってみるまでもない」
先生は言う、
「行けないがな。いわゆる宇宙人に遭うことは夢があるけれども無いだろう。無意味無感動、我々にしたら。数値は全部出ている。五感のうち満足に機能できるのは視覚だけという現場に実際に降り立つことの意味、君は思いつくか。一般の観光客ならまだしも」
「でも先生、下世話なことになりますが、これからの予算申請の際にそういう事実が一応要ると考えます。奴等は科学者ではなく、凡人ですから。頑張っているという印象は、人の脳が読取に時間のかかる大量のデータや高度で理解不能な解説よりも、先生が機密服姿で何か難しいことをして汗をかいている絵一つの方が効果が大きいはずです」
「お前という奴は、どこでそんなことを覚える。ロボットにしておくには惜しい」
先生は助言を入れ、行くことにした。ただし、手前までだ。中芯線が強すぎてかなり危険であり、鉛岩礁にさえぎられる区域以上は踏み込めない。
「こういうものの強度は距離の二乗に反比例する。放散してしまうから、上空からの観察がもっとも適切であり、誰も文句は言わないだろう。お前の言う通りわけのわかる人種ならな」
「先生、話は変わりますが、先ほど宇宙人のことを言われました。無いとおっしゃいますが、全くの零(ゼロ)ですか、可能性は」
「可能性零というのは仮定として成り立たない。仮定が立てられた時点では、未計測の可能性が必ずカウントされている。その時点では零ではなく、空欄だな。理論展開、検証実験を経て計測値が限りなく零ということになって普通零と言うが、人の思考、計測精度に限りがある以上、絶対的に零とは言えないだろうな。ものによっては何パーセントも残されているものもあるが、この星の場合、上位生命体に限っては、はかない夢という以上のものは残っていない」
「お言葉ですが、あそこで動いているのは何でしょう」
「なんだろうな。生命体に有害で今のところ遮断方法のない中芯線の中で動いているのだから、岩かなにかだろう」
「遮断方法がないのは人類の側だけの都合ですし、有害というのも我々の主観です」
「どうもその口ぶりはいけないなあ。変な雑誌をいつも入力してるんだろう」
「ですが、先生、この中芯線の中でも進化展開できる生命体系を発表なさったのは先生自身です」
「発表たって、あれはほとんどいたずら書きの理屈遊びをメディアが取り上げて子供向けに直しただけじゃないか。観測値はいわゆる零だ。何週も前に結論が出ている。まあ、あのおかげであそこからもお金は出たが」
「ではこういう考えはいかがでしょう。我々への政府筋からの指令、つまりいわゆる大義名分ですが、この中芯線の発生原因を突き止め、その人工発生マシンの創造に寄与し、人類エネルギー事情に貢献する。その実、防御困難な新兵器をわが星系側が得るという、大義名分を敵も誰かにのたまってはいないでしょうか。あそこにいるのは人類であり、未知の遮蔽手段を考案した敵側である」
「二つ疑義がある。自慢じゃないがこの有害な中芯線を発見し研究している頭脳は今でこそ二桁になったが二年前までは私一人だった。私以外は皆私の生徒でありどう考えても未熟で私以上と思えんし、皆軍籍があって寝返るのはそれぞれにとって非常に不利だ。つまり、私でさえできない遮断を他人でできる者がいるとは思えん。できたとして、敵に寝返り、私より早くここに来る時間があったとも思えない。これらをすべてクリアした上でも、何も実験動物に自らなる必要はないじゃないか。中は人類ではなく、似人間ロボットということになる、この段階では」
「そうか、先生はそういうときのために私を飼っているんですね」
「そうだよ。飼っているという言い方はまずいが。君は生命体とは違うのだから、使っているのだ。そこのところ、忘れてはいかん」
「あれは遠方ですし、動きも鈍く、こちらに向かっているとも見えないので、もう少し私の疑問をぶつけてみたいのですが、我々が今その縁に載っている岩礁は中芯線を遮断している。違いますか」
「そうだ」
「ならば、答えは出ていると言えないでしょうか」
「理屈ではな。現実的ではないが。このプレートは百キロ以上の厚さがある。縁といえ三十キロだ。減衰率はもっとも厚い部分の約二十分の一。ここは一応安全だが一ヶ月いつづければ、お前のチップパーツのいくつかがただれる。三ヶ月で半分だ」
「怖いですね」
「だろう。岩礁の成分はほぼわかっている。同じものを作るのは可能だ。そして、軍船が厚さ何十キロもの装甲をしょって戦えばいいというのだな」
「話はまた転換しますが、あいつの計測値が出ました。垂直長二・一一m、水平長一・五八m×六・四〇m、この直方体に最大が納まる。地上を東方二時十一分へ平均時速三・四四kmで蛇行様に移動中です」
「蛇行というのは何だ」
「要するに、うろうろですか。体型から言ってスキップという感じではないですね。突起が多数あり、主部分の体積は半分ぐらいらしいですが」
「何だろう」
「動物ですね、うごくものという意味で」
「計測器械が不調であり、私とお前の感覚が幻惑していることなどが同時に起こる確率は計算するのが煩わしいが、まずない。前言撤回だ。いいだろ。あれは生命のあるなしにかかわらず、確かにうごくものだ」
「もっと精密な絵が欲しいところですね」
「うん。船を上に飛ばして撮ろう」
「わかりました。良いお考えです」
しかし、一人と一台を連れて帰る大切な船にダメージを与えない程度近づけて撮った映像でも、大差なくはっきりしなかった。
「しょうがないです、探査機を飛ばしましょう。使い捨て覚悟で」
「浅慮だな。恐竜の類いならいいが、お前の言う敵側、またはいわゆる零の宇宙人だとしても、こちらの存在を教えることになる」
「わかる奴なら、こちらと同様とっくに感知してるのではありませんか。あいつはだから逃げている」
「地上をどこに逃げられる。船を持っている我々から。今焦り気味にだが計算してみたら、この距離の往復には三十五分かかる、そして損傷率は五から十パーセントの間だ。生還の望み十分だ。すぐ直してあげるよ」
「やだ。私はドジですから、先方に気づかれることには変わりありません」
「探査機がいくらすると思ってるんだ」
「あんたは、お金の方が大事なんですか。じゃあ、こうしましょう。今地上をどこに逃げられるとおっしゃいました。待ちましょうよ。恐竜なら物忘れしてまた近づいて来てくれるかもしれないし、別の個体がいるかもしれない」
「あれは遮断のための独特な装甲であっちも船を持っていて、そっちヘ逃げているとしたらどうする。逃げられてしまうかもしれないし、反撃してくるかもしれない」
「反撃なら無線でコントロールするし、逃げるなら船のほうを呼び付けます」
「船は無装甲だろう。後者はない。反撃したくても我々同様純然たる研究班で武器を持っていないなら、前者も無意味、か」
「呼び付ける間だけなら、しかも緊急の場合なら中芯線にさらすことだってあると−−」
「そうだ、今がそうだ。行くのだ。勇気だして。あいつを逃がしてはいけない。何であれ、こっちのものにするんだ。せめて至近で観察だけでもできれば手がかりになる」
それは生物だった。遺伝子解析をすると人類の変異体であることがわかり、しかも五世紀以前のある星のある個体がここに来て変異し、生き続けているという蓋然性がある。知性は残っていず、ただ食って寝ているというだけの代物だった。
「お手柄だな」
「どうす、なおましたか」
「もう少し調整しよう。何を食っていたと思う」
「たに岩礁のえに来てみうから持ち込んだ植物を食べていた」
「たまに岩礁の上」
「そうです」
「違うな。奴は中芯線を浴び続けないと生命維持は無理だ。外来の種汚染から確かに苔類はあるが量が少なすぎる」
「では光合成の一種ですか」
「そうだ。しかしそれだけではない。動物になれなかった同僚と思われる個体が、こちらのほうが圧倒的多数なのだが地面すれすれの地中で生息している。希薄とはいえこの大気成分は彼らの活動によるところ大だ。こいつらをたまに食べてもいるらしい」
「しかし、変なものを見つけちゃったのでは。先生」
「うん。ま、こういうことはよくある。新兵器の見通しは明るくなっていないが、今度は不老長寿の可能性がちらちら見えてきたじゃないか」
「どうして彼らはこの星に来たんでしょう」
「我々と同じか、あるいは遭難したか」
「死ぬとわかっていたはずの岩礁外に入ったわけは」
「岩礁上だって短期で死ぬ。かなりの多数が来てわずかな部分が適応したか。この場合は研究班ではないし、遭難では済まない」
「では、覚悟の渡来ですか」
「言えてるな。お前、頭良くなったぞ」
「へへん。つまり我々のような研究班が何度も来て、適応できると踏んで入植した。あいつは王様で埋まってるのが庶民かな」
「個体数調整の役目じゃなかろうか。動物さんは」
「主役は地中人ですか。こっちには知性があると」
「もう人とは言えそうにないがなあ。根っ子だ。思考してるとしても、時間感覚が長すぎてこちらと疎通は無理かもしれない」
「でもなんで来たんです。もっといい星がありそうなのに」
「中芯線は外敵を近づけないという意味はあった」
「わかった。さっきの不老長寿だ」
「やっぱり馬鹿かなあ。あんなんで生きて何が楽しい」
「集団自殺。宗教上の永遠への昇天」
「よし、根っ子を一体引っこ抜こう」
「私、また」
「平気だ、この崖下すぐのところにも埋まってる」
が、作業時間がかかりかなり損傷してしまった。
「ういといてえ、せせえ」
「何を言ってるかわからんよ。もうだめかなあ」
「ひおいい、せせえ」
「ここかな。どうだ」
「あ、ああ、気持ちいい。さあっぱりす」
「おお。よし、早速だが」
「先生、そこをもう少し。はい、OK」
「死んだよ。やっぱりな」
「え、根っ子」
「今な。これは雌であることがわかった。身ごもっていた。胎児というか、種というか、一緒に死んだ」
「動物のほうは雄」
「そうだろう、まず」
「この葉っぱ、なんかおいしそうですね。茹でると、ああ、よだれ出ちゃう」
「言われてみればな。農場だったという可能性が出てくるな」
「食べてみましょうよ。私だって、味覚あります」
「馬鹿な」
「先生得意の数値はどうなんです」
「無害ではある。お前まず食ってみろ」
「いいでしょう。私は食あたりしないですから。でも、私に茹でさせて味付けもさせること」
茹でる、炒める、蒸すなど幾種もの料理ができた。
匂いを嗅いだだけで先生も腹が鳴っていた。
「どうだ」
「見ればわかるでしょう。美味い。たまんないです。無害なんだから先生もいけば」
「しかし」
「味気ないもんです、船の食事なんて。たまにはこういう役得がなあ。うわわ、信じらんない、このタネ、なんて芳醇」
「よし。食う。人倫なんて、無意味だな、恐竜と根っ子だもんな。どれ」
「むぐむぐ、どうです」
「おお。こりゃあ。むぐむぐ。お前また採ってこい」
「もちろん」
船はずっと軌道を回っていた。
助手は穴掘りの最中ついに機能崩落になり、先生は男性だったのに、身ごもるほうに変わった。
|